符号理論(三年生・春学期)
このページは, 符号理論の講義の受講生との情報交換に使います.
ただし, 今年はあまりまじめに書かないかもしれません.
講義要項と教科書・参考書の紹介
ディジタル情報の伝達はノイズによりゆがめられ, アナログ情報の場合と異なり
それによって致命的な痛手を被る場合もある.
符号理論とは、伝達内容に少し余分なデータを加味することにより, 受信側で
多少の誤りは取り除いて正しい情報を復元することを可能にする数学的手段を
研究するものであり, 数学的理論がプログラミングの工夫などとは本質的に異なる
次元で役に立つことを示す良い見本でもある.
符号理論は, 衛星通信から CD の読み書きなど身近なところまで, 実際に用いられて
もいる.
本講義は符号理論をもっと広く解釈して, 一般に計算機の内部で扱われるコード
というものを対象に, データの符号化, 暗号理論の基礎なども
合わせて解説し, 卒業生に恥ずかしくない程度の知識を与えることを第一の目標とし,
また, 最後は楕円曲線暗号や代数幾何符号などの最先端までたどりつき,
そして卒研でやらせちゃうのを第二の目標とする. ^^;)

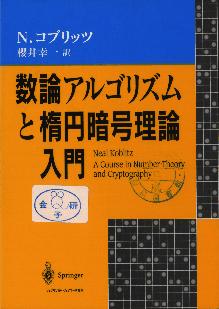 有限体の整数論と RSA, 楕円曲線暗号については, 参考書として
有限体の整数論と RSA, 楕円曲線暗号については, 参考書として
Koblitz: Number Theory and Cryptography, Springer (日本語訳もあります)
を自分で読んでもらう.
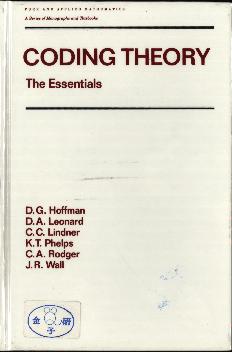 符号理論の参考書としては
符号理論の参考書としては
D.G. Hoffmann et al. Coding Theory, Marcel Dekker
を自分で読んでもらう.
ただし, 3年生の受講者はそんなに恐がらなくても, 遅れないように出席しさえ
すればよい. 特に興味のある人を除いて参考書を用意する必要も無い.
だいたいどんなことをやるかは, 97年度の僕の講義概要の記録を見てください.
【実際の講義概要と予定】
- 4月19日:ASCII コードと漢字コードの話, バイナリファイルを電子メイルで
送るためのコード化の話などをした.
第一回レポート問題
- 4月26日:暗号入門.
第二回レポート問題
- 5月10日:RSA 暗号の数学的基礎の解説をした.
第三回レポート問題
- 5月17日:RSA 暗号の数学的基礎の解説の続きと,
Euclid の互除法の話をした.
- 5月24日:平方剰余と疑似素数の作り方. その1
平方剰余の概念と Legendre 記号の導入をした.
第四回レポート問題
- 5月31日:平方剰余と疑素数の作り方. その2
原始根の存在証明などをした.
- 6月7日:平方剰余と疑似素数の作り方. その3
Solovay-Strassen の疑素数生成アルゴリズムの紹介をした.
第五回レポート問題
- 6月14日:符号理論の基礎を解説した.
- 6月21日:線形符号と巡回符号の基礎を解説した.
第六回レポート問題
- 6月28日:巡回符号とイデアルの対応の話をした.
- 7月5日:巡回符号の双対符号と復号法の話をした.
第七回レポート問題
- 7月12日:巡回符号の構造と作り方について解説する予定.
- 7月19日:最後の講義;巡回符号の構造の続きを解説し,例を計算したあと
簡単な打ち上げティーパーティをやりました.
第八回レポート問題
9月後半に卒業研究ゼミとして, 有限体, 楕円曲線暗号, Reed-Solomon 符号の
解説を続けます. 興味の有る人は続けて参加してください.
 講義科目の紹介メニューに戻る
講義科目の紹介メニューに戻る

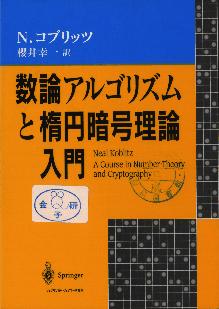 有限体の整数論と RSA, 楕円曲線暗号については, 参考書として
有限体の整数論と RSA, 楕円曲線暗号については, 参考書として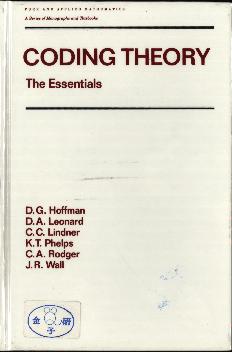 符号理論の参考書としては
符号理論の参考書としては 講義科目の紹介メニューに戻る
講義科目の紹介メニューに戻る